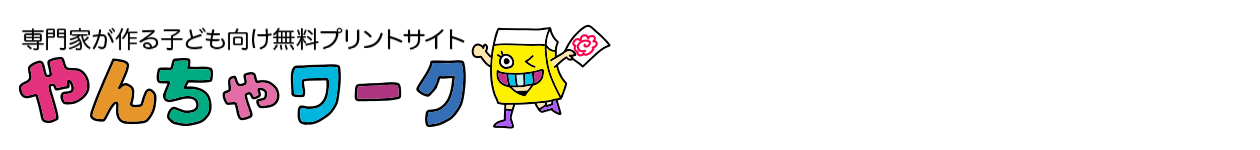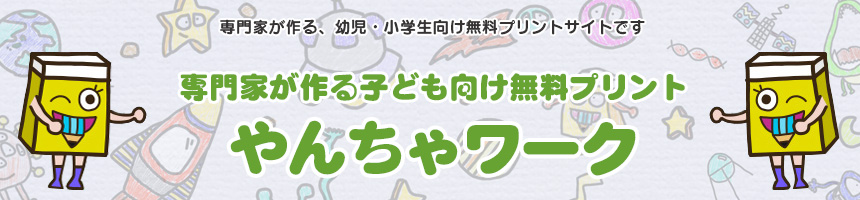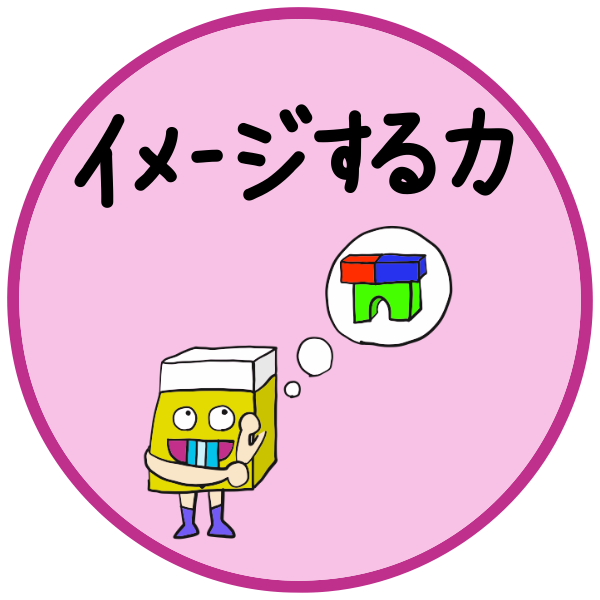このページは、おもちゃ紹介のページです。
管理人は、子どもの発達に関わる心理士として、療育や学習支援、カウンセリングなどを行ってきました。その中で、子どもの発達を助けてくれるおもちゃや教材に多く出会ってきました。
管理人は、『楽しく遊んでいたら、いつの間にか力が育っていた』という状態を、1つの理想としています。
そのため、プリントでの学習だけでなく、おもちゃやゲームを通して自然と力を伸ばしていけたら、とても素敵なことだと思っています。
そこでこのページでは、各課題に応じたおもちゃやお助けグッズの紹介をしていきます。
「気持ちのコントロールが苦手なお子さんには、こんなおもちゃがお勧めですよ」といった紹介を、心理学的な視点でご紹介します。
ご紹介するおもちゃや教材は、公認心理師である管理人が、実際に子どもと使ったり、子どもが使っている場面を見たりした中で、効果を実感した物に限定します。
ただし、ご紹介したおもちゃや教材は、子どもの発達や学習能力等の向上を保証するものではありません。また、ご紹介した物を使用した際の怪我や事故は一切責任を負いませんので、予めご了承ください。
お子さんへの誕生日プレゼントや療育機関・教育機関での備品購入などでお役立て頂ければ幸いです。
本ページはプロモーションが含まれています。
※アイコンをクリックしてください
感情
育てる力
勝ち負けを楽しむ(感情のコントロール)、ルールや順番を守る(社会性)、言葉の理解
おすすめポイント
百人一首として遊ぶのもよいですが、『坊主めくり』のルールで遊ぶのも楽しいゲームです。展開が速く、負けていることがわかりにくいゲームなのもGOOD!
坊主を「ハゲ!」「スキンヘッド!」と言い換えながら楽しく進めることができ、大逆転もあり得ることから、「ゲームって最後までわからないよね」という理解を積み重ねる経験にもなります♪
育てる力
勝ち負けを楽しむ(感情のコントロール)、ルールや順番を守る(社会性)、言葉の理解、数概念、目と手の協応
おすすめポイント
すごろくは、『負け続けている』ことや『差が開いてきている』ということが目で見てはっきりわかるため、ある程度勝ち負けの受け入れができるようになってから取り組むことをおすすめします♪
育てる力
勝ち負けを楽しむ(感情のコントロール)、ルールや順番を守る(社会性)、言葉の理解、人とのコミュニケーション、お金の計算、数概念、目と手の協応
おすすめポイント
大人も楽しめるゲームですので、家族みんなで楽しむことで、よい親子関係の形成にもつながります。決して安いゲームではありませんが、作りがしっかりしているため長く遊べるゲームです♪
育てる力
勝ち負けを楽しむ(感情のコントロール)、ルールや順番を守る(社会性)、言葉の理解、人とのコミュニケーション、お金の計算、数概念、目と手の協応
おすすめポイント
人体模型に内臓や骨のパーツを埋め込むゲームです。緊張感があるゲームですので、ドキドキすることが苦手なお子さんには避けましょう。「ドキドキすると、手がぎゅーってなるね」「ドキドキすると心臓がバクバクいうね」など、身体の変化を言葉にして伝えるのもよいでしょう。「ちょっと落ち着こう。深呼吸してからやろうか」などと伝えることで、自分で気持ちをコントロールする練習にもなります♪
お助け教材
育てる力
見通しをもつ、気持ちを切り替える
おすすめポイント
『遊んでいると切り替えが難しい!』といったお子さんに、おすすめのグッズです。また、時間の経過を実感しにくいお子さん、見通しがないと不安になりやすいお子さんに対しては特に使いやすいタイマーです♪
育てる力
集中力、安心感
おすすめポイント
特定の音を怖がるお子さん、聞こえてくる音が邪魔で注意が散漫になりやすいお子さんなど、聴覚過敏のあるお子さんに試してみていただきたいアイテムです。
イヤーマフは、低音から高音までの騒音を遮断します。そのため、話しかけられても気づきにくいというデメリットはありますが、集中したい時や特定の音(例:雷や掃除機の音)を遮断したい時は有効なグッズです♪
育てる力
集中力、安心感
おすすめポイント
デジタル耳せんは、イヤーマフとは異なり、騒音をカットして人の声だけを聞こえるようにしてくれます。
学校のアナウンスや相手からの言葉が聞こえるところがよいところです。
お子さんの特徴に合わせて選択してみてください♪
イメージする力
育てる力
想像力、見立てる力、人とコミュニケーションをとる力、遊びを共有する力、手先の操作
おすすめポイント
病院に行くことや健診を受けることに大きな不安を感じるお子さんについては、こういった遊びを通して不安を和らげていくのもおすすめです。
お子さんと役割を交代しながら、コミュニケーションを楽しみましょう♪
育てる力
想像力、見立てる力、人とコミュニケーションをとる力、遊びを共有する力、手先の操作
おすすめポイント
レジやお金、焼き窯、ショップバッグやトレイなど、リアルさの中に子どもたちの心を惹き付ける魅力がたくさん詰まったおもちゃです。
パンをレジに通すとレジが光ったり、パンが焼けると音楽が流れたりするところがとても楽しく、その度に子どもと大人が目を合わせ、笑い合うこと(感情の共有)が自然とできるおもちゃです♪
育てる力
想像力、見立てる力、手先の操作、数概念、社会性、コミュニケーション
おすすめポイント
とっても可愛らしいおもちゃです。このおもちゃは、完成したものが失敗になることはありません(どんなデコレーションでも可愛く仕上がります)。
そのため、お子さんの達成感も大きいおもちゃです♪
育てる力
想像力、見立てる力、人とコミュニケーションをとる力、遊びを共有する力、手先の操作
おすすめポイント
色のついた粘土は、『赤色はトマトにもなるし、苺にもなる』といった見立てる力を育ててくれます。また粘土は、こねる、丸める、伸ばす、つぶすなど、非常に多くの手先の操作を経験することができる、とってもよい素材です♪
※小麦粉アレルギーのあるお子さんには、寒天粘土や米粉粘土を探してみてください。
育てる力
問題解決力、社会的なルールの習得、文脈理解
おすすめポイント
『ソーシャルスキルトレーニング』で使うことの多いカードです。カードの裏には、お子さんに問題を出す時の大人側のセリフやポイントが書かれているため、非常に使いやすいカードです。値段が高いですが、110枚入っており、各カードのねらいも書かれているため、お子さんへの指導場面や学習で使用するにはよいアイテムだと思います♪
育てる力
文脈理解、人の気持ちを考える
おすすめポイント
カードは全部で52枚入っており、そのうち4枚は感情のカードです。
12種類のストーリーを作ることができますが、1度使ったらおしまいということはなく、登場人物に名前をつけたり、吹き出しをつけてセリフを考えたり、人物の感情を考えたり、3枚目以降のお話を自分で作ったり…ゲーム感覚で様々な力を育ててくれる教材です♪
育てる力
状況の理解、文脈理解、社会的なルールの習得、暗黙のルールの習得
おすすめポイント
このカードは、場面設定や子どもに身に付けてもらいたいスキル別に分かれて売られているため、お子さんの様子に合わせて選択しやすい教材です。
カードに書かれているイラストを見て、『どういう状況か』『周りの人はどんな気持ちか』『この後何が起きるか』『どう行動すればよいか』を考えることができるため、ゲーム感覚で楽しく学べる教材です♪
社会性・コミュニケーション
育てる力
ルールや順番を守る(社会性)、相手の手を読む(他者視点)、勝ち負けを楽しむ(感情のコントロール)
おすすめポイント
ルール自体は単純で覚えやすいため、ルールを守ることだけに気を取られるのではなく、相手と遊んでいることを意識しながら遊べるゲームです。遊んでいるうちに自然と考える力が身に付きます♪
育てる力
ルールや順番を守る(社会性)、相手の手を読む(他者視点)、勝ち負けを楽しむ(感情のコントロール)
おすすめポイント
駒に動きの矢印が書いてあるため、丁寧に将棋を学べるおもちゃです。何歳になっても楽しめるゲームですので、休日に家族であそぶのもよいですね。最初は勝ち負けにこだわらず、まずは将棋を楽しむところから始めてみましょう♪
運動
育てる力
想像力、空間認知、手先の操作、集中力、論理的思考
おすすめポイント
LaQは、手先の不器用さがあるお子さんも熱中して遊ぶことが多いおもちゃです。パーツのカラフルさ、パーツがはまった時の気持ち良さ、作った物で遊べる楽しさ、立体的な物が出来上がった時の達成感など、理由は様々かと思います。
特に、”手先は不器用だけど、物を組み立てたり形を見たりする力が強いお子さん”には、ぜひLaQでの遊びを通して手先の操作を育てて頂けたらと思います♪
育てる力
想像力、空間認知、手先の操作、集中力
おすすめポイント
パーラービーズの良いところは、プレートに好きな色をはめていくだけで完成度の高い作品になる所です。プレート自体が意味のある形(例:ハートやクマの形)をしているので、完成品が失敗になることはありません。また、アイロンをかけることでアクセサリーとして持ち物に付けられる所も素敵ですね。子どもたちがよく、「これ自分で作ったんだ!」と誇らしげに見せてくれます。リュックに付けてあったりすると、色んな人から褒めてもらえる機会ができるので、それもまた子どもの自信につながります♪
育てる力
空間認知、手先の操作、集中力、想像力、力のコントロール
おすすめポイント
色や大きさが様々な輪ゴムが入っているため、はめる輪ゴムによっては指先に入れる力加減が変わってきます。特に、『いつも力を入れすぎてしまう、力加減がわからない』というお子さんには、繊細な輪ゴムを扱うという経験が、力の入れ方をコントロールする力を育てることにもつながります♪
記憶力
育てる力
記憶力、想像力、コミュニケーション、社会性
おすすめポイント
このカードのすごい所は、『裏返すと全て同じ形なのに、表の絵柄は全然違う!』という所です。特に、テディベアだけではなくパンダの絵柄もありますので、子どもたちがとても驚くのです。「ねぇ、見て!同じ形なのに絵が違うんだよ!」と気付いて教えてくれる子もいました。
一般的な神経衰弱は、『見たことを記憶すること』に繋がる遊び方ですが、テディベアに名前を付け、1枚ずつカードを出して名前を言い合うという遊び方では、『聞いたことを記憶すること』にもつながります♪
育てる力
記憶力、コミュニケーション、社会性
おすすめポイント
何年経っても大人気のはらぺこあおむしです。子どもに「これやる?」と尋ねると、高確率で「やる!」と答えてくれます。様々な色使いと特徴的な柄がプリントされており、人によってはやや刺激が強いと感じる方もいらっしゃるかと思います。目で見た情報(視覚情報)が頭に入ってきやすいお子さんには、刺激が強過ぎるため、『探すこと』に苦労するお子さんもいらっしゃいました。「それでもやりたい」のか、「疲れてしまうからやりたくない」のかはお子さんによりますので、お子さんの特徴を踏まえた上で遊びましょう♪